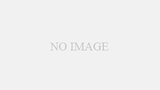「うちの子、外では別人?」学校で大人しい子が家で感情爆発
「ちょっとしたことで癇窻したり、私に八つ当たりしたり。まるで別人のよう。」
「学校では いい子 なのに、家では別人のように荒れる――」
このギャップに、あなたは一人で悩んでいませんか?
「もしかして、私の育て方が悪いのかな?」「学校で何か嫌なことがあるの?」…そんな風に、不安になったり、自分を責めてしまったりしますよね…。

わたし自身、息子の“帰宅後癇癪”に翻弄され、学童へ迎えに行く足取りが重くなった元教員ママです。
この記事では 、
①原因の正体 → ②わが家の小1の壁乗り越え方→ ③驚きのビフォーアフター
をお届けします。もしあなたが今、同じような悩みを抱えているなら、この記事が、少しでもあなたの心を軽くし、未来への希望につながるヒントになれば嬉しいです。
1.小1「帰宅後癇癪」に親が疲弊した日々
小学校に入学しすぐのことです。学童にお迎えに行くと、何を言ってもすぐに怒り、「〇〇のせいだ!」と八つ当たりをされる日々。時には物を投げつけたり、イヤイヤ期のような強い拒否を示したり…。(後から思えば、まさにストレスを怒りで発散していたのでしょう。)

とにかく、受け止めようと、下記の手立てを打ちました。が、全滅です。
| 試したこと | 効果 |
|---|---|
| 抱きしめて共感 | その場でさらに暴れる |
| クイズ大会や冗談で笑わせる | 無視・怒り出す |
| そっと放っておく | 何かの文句をいいだす |
| 寄り添う。困ったことあったらなんでもいってね! | なにもない! |
「どうして家でだけこんなに荒れるんだろう?」 「私との関係が悪いのかな?」 「こんなに癇窻がひどいのは、私の育て方が悪かったんだ…」
自分を責め、出口の見えないトンネルにいるような気分でした。学童に迎えに行く時間も、また始まる「嵐」を思うと、正直しんどかったのを覚えています。

2.授業参観で見えた“休み時間迷子”
入学直後、授業参観がありました。コロナ中なのでオンライン授業参観。
そこで気づいたのです。【あ、これか!】と。
①休み時間、カメラに手を振りアピールしようと群がる子供たち。

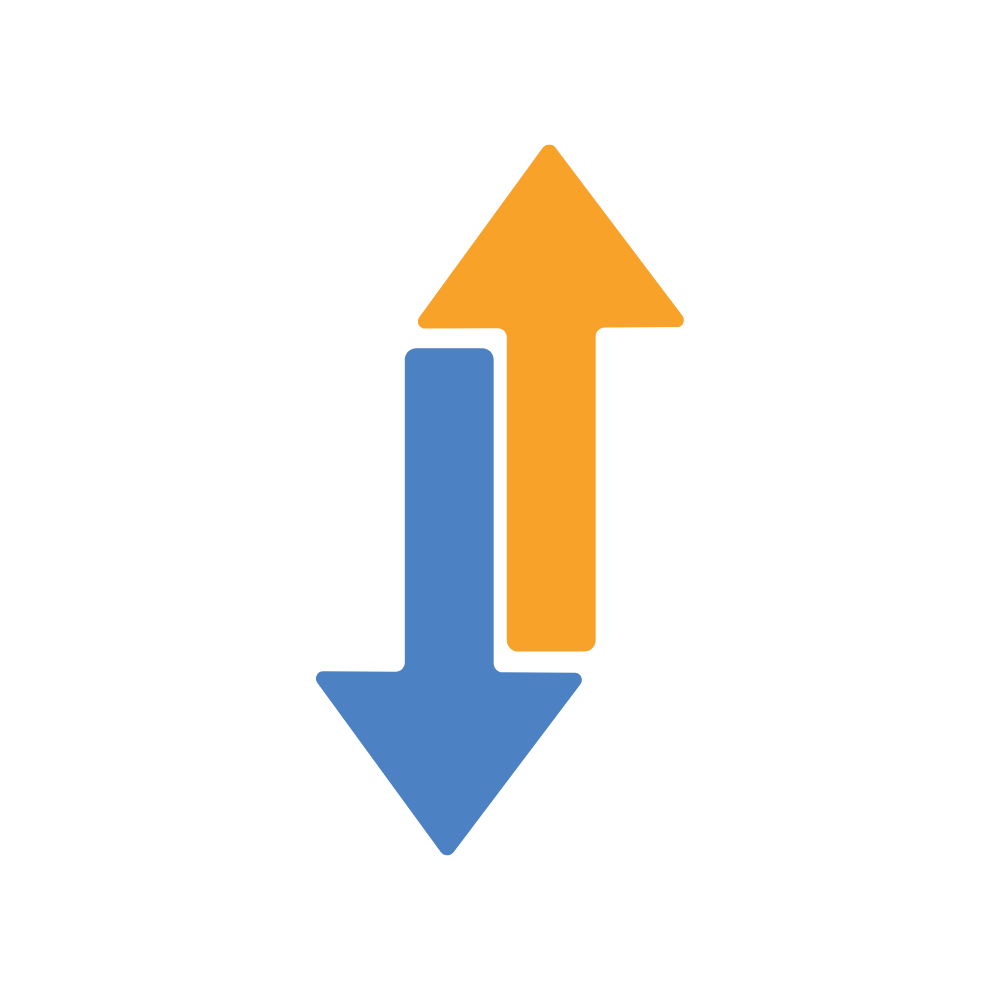
じっと自分の席にすわって、前を見つめて動かない息子

②授業中にもかかわらず、先生の声もかき消されるくらい、落ち着かない新1年生の教室。

慎重・繊細な息子は、集団のルールから外れる子が気になったり、集中したくても、騒がしさが気になってしまったり、、気づかない間に、ストレスのコップがたまり続けていたのです。
そのうえ、休み時間、遊ぶ友達がいないから、そのストレスが解消できず、たまり続けているんです。
そう、家が彼にとって、唯一「武装解除」できる、心から安心できる場所だったのです。
①教室での騒音
②ルール無視の児童に過敏
➂遊び相手がいない→ 発散ゼロ

これは、慎重な子や繊細な子によく見られる、頑張り屋さんのサインなのです。
3.学校や専門機関の「見守り」では足りなかった理由
家での息子の様子を見て、これは専門家の力を借りるべきだと考えた私は、学校の先生やスクールカウンセラー、学童の先生に相談しました。
しかし、、、

授業態度は問題ないので様子を見ますね

もっと大変な子もいますので…おうちでの癇癪は…
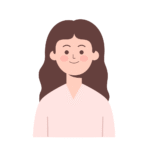
もう1年生なんだから、自分から話しかけないと
学校での様子を見ている先生方からすれば、教室でトラブルを起こしているわけでもなく、指示に従えている我が子は「問題ない子」に見えるのでしょう。
親である私が家で直面している激しい感情の爆発は、そこでは理解されにくい現実がありました。

結局、家で起きていることは、家の問題なんだな…
誰も頼れない、、という孤独感を感じましたが、「誰かに頼るのではなく、親である私が、この子に必要な環境を、試行錯誤しながら作っていくしかない」と、腹を決めました。

①校内では「静か=手がかからない子」扱い
②家庭での爆発は 可視化されにくい “隠れ困りごと”
➂結果、親は孤立し「わたしの育て方が悪い?」と思い込む
4.小1の壁乗り越え方3ステップの全体像
「親である私が、この子に必要な環境を作る」そう決意した私は、大きく分けて3つの具体的なことに取り組みました。
【取り組み1】言葉かけで小1の壁乗り越え方をサポート
まず、原因がなんとなく分かってきたところで、息子への言葉かけを見直しました。学校でのストレスや、彼が特に負担に感じているであろう友達関係の話題は避けることにしたのです。
- 漠然とした質問や友達関係の質問をやめる
「学校どうだった?」といった漠然とした質問や、「友達と遊んだ?」「誰と仲良くしてるの?」といった友達関係に踏み込む質問は一切聞かないことにしました。
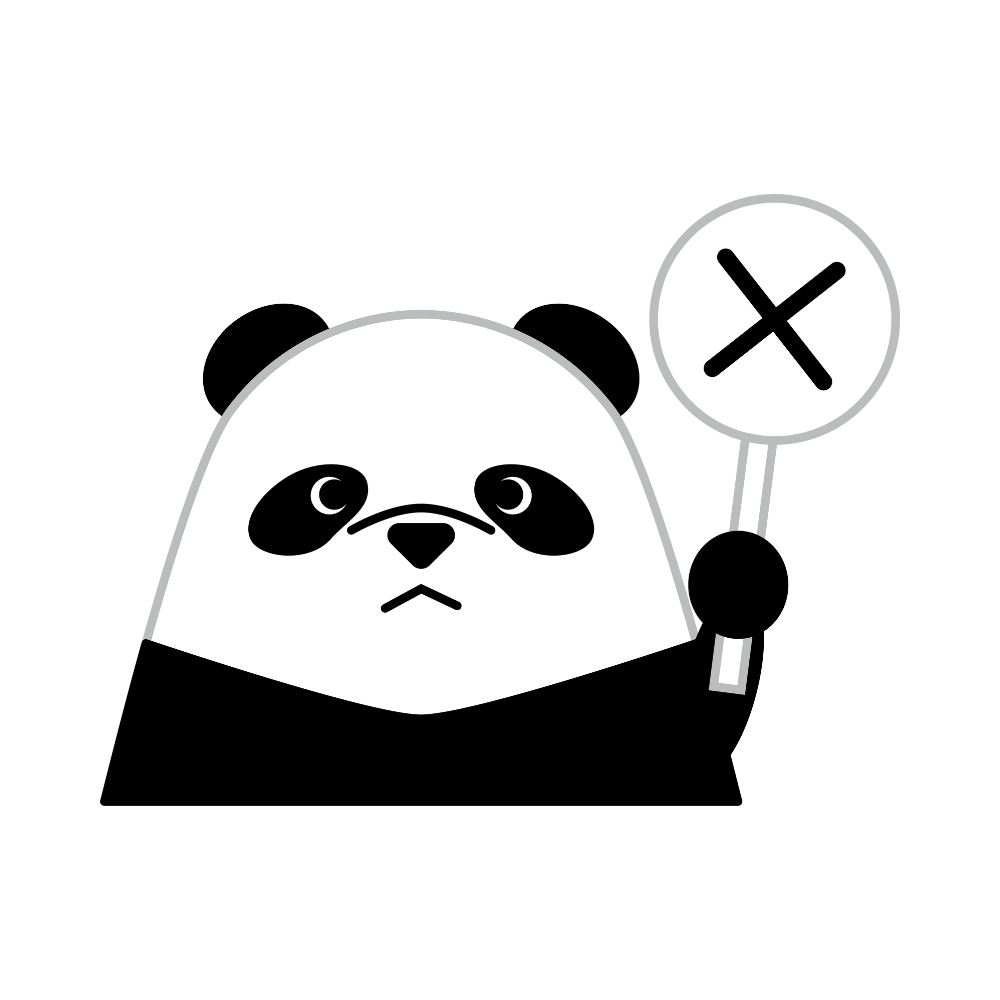
これは、彼が言葉にしたくないこと、あるいは学校での負担を思い出させてしまう可能性のある質問だと考えたからです。(実は幼児期に「どうして友達と遊ぶ約束をしないの?」と言って失敗した苦い経験もありました…)
- 客観的で答えやすい話題に絞る
その代わりに、こどもの好きな給食の献立や、授業の内容など、こどもが比較的答えやすく、事実ベースで話せる話題に絞りました。

今日の給食何だった?(献立を事前にチェックしておいて)唐揚げ何個ずつだった?

算数は何を勉強したの?足し算かな?
具体的に聞くようにしました。もちろん、「しらない!」と不機嫌なときもあります(笑)。
でも、もし答えが返ってくると、あ、今日はそこまでのストレスではないのかな、という彼のバロメーターになったりもしました。
- 褒める機会を増やす
授業の話題は、「あら、よく覚えているね!」「先生の話、ちゃんと聞いてるんだね、すごいね!」と褒める機会にも繋がります。学校での「頑張っている部分」に光を当てることで、彼の自己肯定感を少しでも上げられたらと考えました。

- 「みんな違って、みんないい」を伝える
また、直接的に「友達いなくてもいいんだよ」と言うと、彼が「いるもん!」と怒り出したりもしたので(笑)、少し遠回しに、「みんな違っていて、みんないいんだよ」というメッセージを伝えるようにしました。
黒柳徹子さん、エジソン、森鴎外、アインシュタインなど、ちょっと風変わりだけれど、自分の道を貫いて素晴らしい功績を残した偉人の話をしたりしました。(変人だったんだってーとおもしろく)
学校で孤独を感じているかもしれない彼に、「そのままで大丈夫なんだよ」ということを伝えたかったのです。

そのままで大丈夫なんだよ、色んな人がいるからね
| NG質問 | 置き換えた質問 | ねらい |
| 「学校どうだった?」 「友達と遊んだ?」 | 「給食は何だった?唐揚げ何個?」「算数は何を習った?」 | ★漠然→具体に。ストレス源(友達関係)を避け、 好きな給食・授業で“思い出し笑顔” を引き出す |
| 「友達作りなよ」 | 言わない | “出来ていない点”の指摘は自己肯定感↓ |
①返答が「知らない!」でもOK → 感情のバロメーター として観察
②機嫌が良い日は “ちょっと変わった偉人トーク” で価値観をひらく
例:黒柳徹子・エジソン・アインシュタイン──「みんな違っていい」
【取り組み2】習い事で小1の壁乗り越え方を実践
学校で頑張って、家で感情を解放する…このサイクルの中で、
彼が本当に「ホッとできて、自分をありのまま出せる第三の場所」を持つことが、心の安定に不可欠だと強く感じました。また、居場所ができれば、家での癇癪も減ると思いました。
そこで、習い事での「居場所」づくりに力を入れることにしました。
習い事選びの基準
単に何かを習わせるのではなく、自己肯定感の上がる「居場所」になり得るかどうかの基準で探しました。
- 少人数制:
繊細な子や慎重な子は、大人数や騒がしい場所が苦手です。少人数であれば、落ち着いて活動でき、先生や友達との関わりも負担になりにくいと考えました。

- 本人の「好き!」を尊重:
私がやらせたいものではなく、息子自身が心から「やってみたい!」と思えるものを最優先しました。 - 評価や競争が厳しすぎない:
結果を出すことよりも、過程や楽しむこと、または個人プレーの運動に重点を置いている場所を選びました。自己肯定感を下げるようなプレッシャーは避けたかったのです。

- 運動系:
学校で溜め込んだエネルギーを、安全な場所でポジティブに発散できる運動系の習い事も選択肢に入れました。
| 選定基準 | 実際に選んだ例 | 教育的メリット |
| ① 子どもが「やってみたい」と即答 | 体操教室/スイミング/ロボット工作/オンラインなど | 興味ドリブン → 継続◎ |
| ② 評価・競争がゆるい | 少人数制または、プールのような個人競技、画面オフのオンライン | 安心安全の場=自己肯定感↑ |
| ③ 送迎はファミサポ | 時短勤務でも負担分散 | 親のストレス軽減=家庭の安定 |
体験と決断、そして費用
いくつかの習い事を体験した結果、息子は「全部やりたい!」と言いました。正直、費用は重くのしかかり、家計は火の車になりました…。

時短勤務の私にとって、決して楽な出費ではありませんでした。
しかし、この時、私は「今がお金のかけどきだ!」と覚悟を決めました。
日々の親子バトルの疲弊、このままでは息子の自己肯定感が下がってしまうかもしれない不安、今後思春期を迎えてもっと複雑になる可能性…
今、この子の心の基盤を整えることに投資することが、将来必ず活きてくると信じたのです。送迎の負担を減らすためにファミサポなども活用し、どうにか習い事を続けられる体制を整えました。


①💸 月の出費・・貯金の取り崩しは痛い… でも「今こそ投資期」と割り切り。
②反抗期に入る前に 非認知能力(自己主張・協働)を安全に練習できる価値はプライスレス!
*ちなみに、自己肯定感🆙と居場所ができたので、中学年で2つ減り、高学年でさらに1つ減りました。
❝教育的視点❞なぜ習い事が「居場所」になりやすいのか?
学童が居場所になれば一番良いのですが、繊細っ子は初めての場所や大人数の環境、騒音が苦手な場合が多いです。
その点、少人数の習い事や、運動系の習い事には、学校とは違う良さがあります。 学校で溜め込んだストレスやエネルギーを、安全な場所でポジティブに発散できるだけでなく、学校とは異なる人間関係、役割、評価軸の中で活動することで、
「自分は学校とは違う場所でも通用するんだ」
「ここなら自分を出せる、楽しい!」

という成功体験や安心感が得られます。この経験が自己肯定感を育み、心の安定に繋がっていくのです。
【取り組み3】週末リフレッシュで小1の壁乗り越え方を定着
平日、学校や習い事で気を張って頑張っている分、土日は家族でゆっくり過ごしたり、思いっきり楽しめたりする時間を作ることを意識しました。
遠方に毎回行くのは大変なので、近場の科学館や、一歩先の市のイベントなど、子どもが興味を持ちそうで、かつ家族みんなで楽しめる場所を探しまくりました。


これが、平日「今度ここに行こうね!楽しみだね!」といった、学校以外のポジティブな話題転換にもなり、彼の気持ちを少しでも明るく保つ手助けになったと思います。もちろん、「ゆっくりする」ことも大切なリフレッシュでした。
①近場の科学館・図書館・無料ワークショップ を徹底リサーチ
②平日から「次の土曜は〇〇行こうね!」と “楽しみ貯金” を作り、話題転換
➂大自然より “一歩先の市のイベント” → 移動ストレスを最小化
5.ビフォー→アフター:「居場所」がもたらした驚きの変化!家での癇窻から学校でのリーダーへ
言葉かけの見直し、習い事での「居場所」づくり、そして週末のリフレッシュ。これら3つの取り組みを続けていくうちに、少しずつ、しかし確実に変化が現れ始めました。


一番分かりやすかったのは、家での癇窻の頻度が減ってきたこと。
特に、習い事を始めて数ヶ月経った小学1年生の秋頃には、帰宅後の「嵐」が嘘のように落ち着いてきました。学童が辛かったのか、習い事が楽しかったのか…どちらか、あるいは両方の効果だったのでしょう。
その後、小学2年生でクラス替えがあり、また少し帰宅後の不穏な時期もありましたが、以前ほどのひどさではなく、頻度も落ち着いていきました。
そして、私にとって何より嬉しく、驚きだったのは、彼の学校での変化です。
かつては「絶対手を上げない」「自分を出すのが苦手」だった彼が、なんと小学3年生では手を上げて自分の意見を発表できるようになりました。そして、なんと班長やリーダーに立候補するまでになったのです!

この変化は、単に習い事のスキルが上がったからではありません。
習い事という学校以外の「居場所」で、安心して自分を出し、自己肯定感を育めたことが、彼の内面に大きな自信を育み、それが学校での積極性へと繋がったのだと感じています。
学校にも、ようやく彼にとっての「居場所」ができたのでしょう。
*自己肯定感と居場所ができたので、中学年から習い事は2つ減り、高学年で1つ減りました。「成長したし、お金もかかるから、整理しようか」と話し合いを行いました。
| 学年 | 家での癇癪 | 学校での姿 |
|---|---|---|
| 1年 | 週5回 | 発表ゼロ |
| 2年 | 月2回 | 「発表しない宣言」 |
| 3年 | ほぼゼロ | 手を挙げる常連/ 班長やリーダーへ |
6.まとめ:あなたの家の子は大丈夫!今日からできること
「学校では大人しい、家では…」というギャップに悩むお子さんの姿は、親にとって本当に辛いものです。しかし、それは決してあなたが一人で抱え込む問題ではありませんし、お子さんが「悪い子」になったわけでもありません。
それは、外の世界で頑張っている心が、最も安心できる場所である家で、ようやく自分を解放している証拠なのです。そして、そこには必ず理由があります。


私たち家族は、「子どもの行動の背景にある理由を理解し、家以外の『安心できる居場所』を作ってあげること」が、状況を大きく変えるカギになることを経験しました。
①家で荒れるのは 「家=安心基地」 の証拠
②原因は「休み時間迷子」など“外で溜めたストレス”
➂学校外の居場所づくり が自己肯定感と非認知能力を育む
あなたの家のお子さんも、きっと自分の輝ける場所を見つけられます。完璧を目指さなくても大丈夫。

まずは、今日からできることから、少しずつ「種まき」を始めてみませんか?
①お子さんの好きなこと、興味があることを、否定せず「面白そうだね!」と観察してみる。
②放課後、お子さんの気持ちに寄り添う時間を作る
(たとえ短時間でも「疲れたね」と共感する)。
➂友達や学校の不満はとくに「辛かったね…」と寄り添い、どうしていこうか本人と話し合う。
④好きの種を10個書き出す。
➄帰宅後 15分、親子で“静かな充電時間”を設定する。
⑥夜、読み聞かせをしてみる。
➆学校や家ではない、お子さんが「ホッとできそう」「楽しめそう」な場所や活動(少人数の習い事、公園、図書館、家族でのお出かけなど)を一緒に探してみる。
⑧休みの日に自然体験をしてみる。
この経験が、今まさに同じ悩みを抱えるあなたの、そしてお子さんの可能性を広げる「種まき」の一歩となれば幸いです。
【最後に】
私のブログでは、今回のような「子育て探究」のリアルな体験談に加え、子どもの「やってみたい!」を引き出す「旅育」「英語育児」「非認知ワーク」に関する情報も発信しています。これら全てが、子どもの可能性を広げ、「学びは楽しい!」を実感するための「種まき」だと考えています。
子どものことで悩んだり、もっと可能性を伸ばしてあげたいと感じたりする時に、このブログがあなたの力になれたら嬉しいです。
【著者プロフィール】
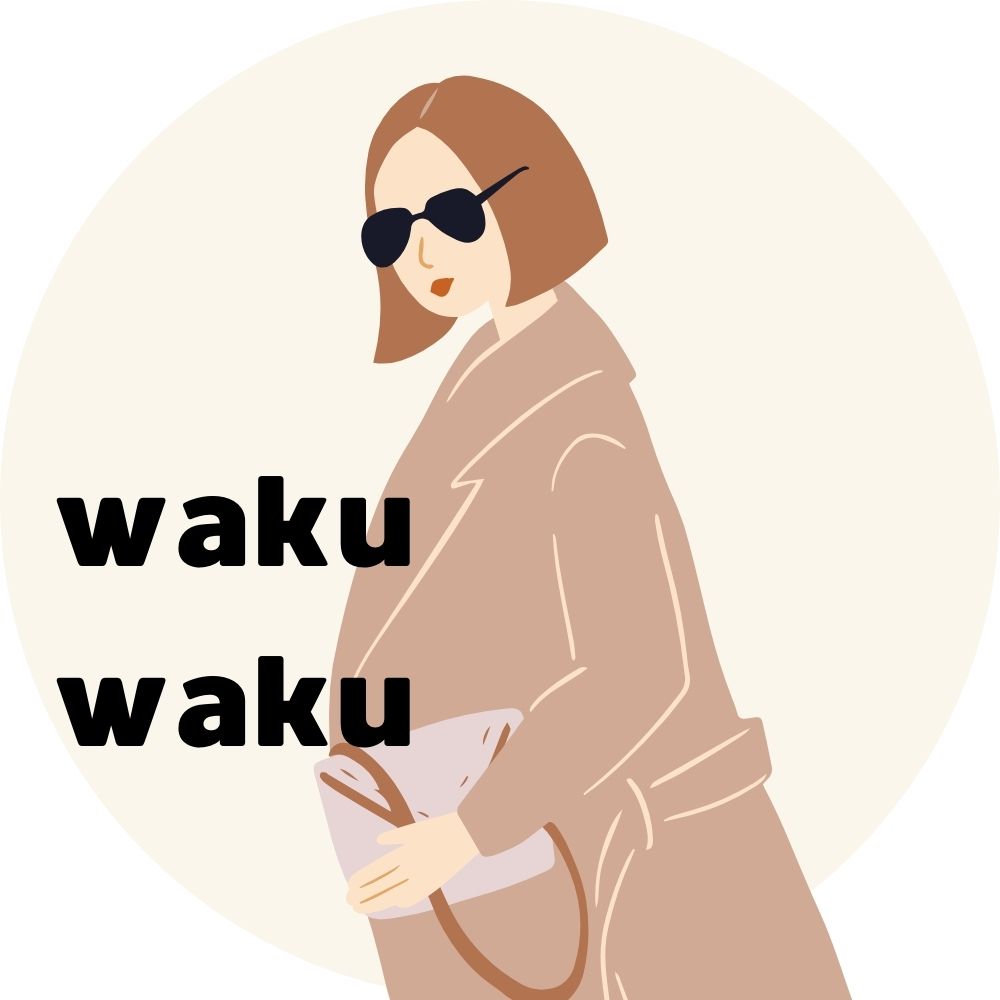
子どもの“やってみたい!”を咲かせる種まきママ🌱
┗ 元小学校教員 / 現インターナショナルキンダー講師
┗8年で慎重っ子→主体的チャレンジャーに変身させた実体験ストーリー⚡
\学びは楽しい!がモットー🌱子どもの可能性を伸ばす種まきが好き/ ✈️旅育|📚おうち英語|🌟非認知能力情報 をシェア中